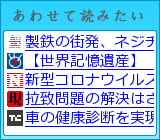2007年10月24日
LindenLabが日本をどう考えているか知りたい
リンデン副社長に聞く、日本におけるSecond Lifeのあり方(ascii.jp)という記事を読んで気になっていたのでメモしておくことにします。
...プラットフォームとして考えた場合は事情が変わってくるでしょう。(プラットフォームを生かすという観点では)日本の企業のほうが、日本人に最適なサービスやエクスペリエンスのあり方を知っているはずですし、どのようなサポートが適しているのかも理解しているはずです。
...私たちが「日本人特有の考え方」や「日本国内のビジネス」の本質的な部分をすべて理解するのは不可能なんです。
「It is your market, you know the best」(日本市場については、日本人がもっともよく知っているでしょ?)ということを言いたいのです。
ということで、サポートについては以前Office Hourとか日本語サポートとかというエントリーでも少し触れた「コミュニティー・ゲートウェイ・プログラム」「グローバル・プロバイダー・プログラム」に期待ということだと思います。
LindenLabのゴールは何かと聞かれて
一言で言えば、柔軟性のあるバーチャルワールドプラットフォームを提供し続けていくことです。
と答えているのに
...「プロダクト」としてのSecond Lifeと「プラットフォーム」としてのSecond Lifeは切り分けて考えなければならない...
とも答えていて、そのプラットフォームとして捉えた部分は前述のように日本人がやればいいじゃん、と書かれており、少し理解しづらい内容になっています(LindenLabはどこまでをサポートすべきと考えかについて)。
言いたかったことは「SecondLifeというプラットフォームを支えるシステムの動作は保障する(ように努力する)」だと思いますが、線引きがイマイチわかりずらくユーザーからの期待とLindenLabが考えるサポートにズレが起きること請け合いのように思います。この辺り、以前Nockさんが書かれていたことは正にそのとおりで、やはり共通の認識が必要だと感じます。
もっとも英語版意外は全てベータ版なので、英語以外でのサポートはそもそも期待し過ぎてはいけないのかもしれません。
今度はサポートとは別の部分です。前述の「日本の企業の方が~」という部分を受けて次のように質問しています。
そのメッセージは誤解を招きそうです。積極的に動く米国人の体質とは異なり、日本人は「何かしらの箱」を与えられるべきと考えることが多いのです。
これに対してこの副社長さんは次のように答えています。
確かに「プラットフォームだけを提供しているのだ」という言い方では「え? 自分たちで全部やれというの? サポートをしてくれないの?」という意味に受け取られるかもしれません。
しかし、これは“関係ないよ”という意味ではまったくないんです。
質問者側はSecondLifeをネットゲームのようなものとして捉えた場合に、LindenLab側がコンテンツ自体用意していないと何して良いかわからないのではないか、と言ってるように思います。どこまでサポートするつもりがあるのかというサポート体制の方に話を進めるのかと思ったのにちょっと意外でした。事実、回答側は「サポート」の面も気にして回答しています。
ゲームとして捉えれば確かに何か用意されていた方が面白いという人が居て当然ですが、それはまさしく日本人の好みにあったコンテンツを誰か(LindenLabである必要はない)が作れば良いのであって、今更この点をついてくるとは思いませんでした。そう聞かれてしまえばLindenLabとしても「日本市場のことは日本人が一番よくわかるでしょ」と答ええるのも当たり前のように思います。
コンテンツの充実や楽しみ方の面で、それほど米国人と日本人の特質の違いを心配する必要があるのでしょうか。元記事を見ればわかるように、インタビュアーはどうもChizzyさんのようです。ご本人は(私よりははるかに)楽しみ方を知っていて日本のin world事情にも詳しい方です。そのChizzyさんがこういったインタビューを展開するということは、日本人が自前でコンテンツを用意して盛り上がるのは難しいのではないかと心配されているのでしょうか。「何をして良いかわからない」という声を心配する必要性を感じていなかったので、この点が非常に気になっていました。
よくよく考えてみるとこのインタビューは「月刊アスキー」に掲載されるそうで、まだまだSecondLifeが「どんなものか」知らない人の方が圧倒的に多いわけです。インタビュアーはそういう人が抱くであろう疑問に触れる必要があります。考えてみれば当然のことながら、このインタビューを読んだ時点ではかなりの違和感を感じたというわけです。まだChizzyさんの意図するところを理解できたか不明ですが(^_^;)
LindenLabが日本という市場についてどう考えているのか全くわからないなぁと思っていたので、このような当事者の声が聞けるのはありがたいと思います。逆にユーザー数多いんだからもっと日本について真剣に考えて欲しい(考えていたら情報発信して欲しい)とも思います。というお話でした。
2007年10月22日
LSL convention Japan -2007
なぜかLSL convention Japan -2007の話題です。ご存知でない方はリンク先を見て頂ければわかりますが、10/20~28の期間にLSLに関する展示と交流会が行われるというイベントです。
3つのSIMにそれぞれ異なる内容の展示があり、交流会には全部で11のテーマがあります。かなり直前になってテーマが面白そうであることに気づき、急遽交流会にも参加してみることにしました。この週末の感想をメモしておこうと思います。
展示
先に展示について少し触れておきます。土地レンタルの管理用スクリプトのようなツールではなく、その場で単純に遊べる、体感できるものが多く展示されていました。どんな命令を使って作ってあるというNotecardも用意されていて、動作を見ただけではスクリプトの内容がピンと来ない人にも親切な展示だと思います。交流会でも発言のあった話ですが、このような展示は「スクリプトの製作を依頼する側」にとっても意味がある(誰がどんな物を作れるかわかるので)ということで、今後もこういった場(一箇所で様々な物を見れる場所)があると良いと思います。
交流会
この週末にあった4コマ全てに参加してしまいましたが、結果としては得るところがありました。スクリプターの人達はこもって一人で作業しているというケースが多いようで、たまにこういう交流があると良い刺激になるという点で意見が一致していたように思います。
ログも公開されているので、発言する気がない人も後から読むことができます。進行上の問題として「初心者が着いていけずに黙ってしまっているのではないか」と心配して下さる方がいらっしゃいましたが、少なくとも自分の場合は黙って聞いているだけでも参考になるセッションが多かったです。
テーマは決まっているものの、集まったメンバー次第で脱線もするし自由におしゃべりできる状態でした。中には司会進行の方がリードしてほぼ脱線もなく話が進むというセッションもあり、対照的でした。基本的には後者のスタイルが良いなぁと思いましたが、盛り上がり方次第では多少入り乱れていくつかの話が平行して進むのも面白いとも感じました。テーマについて掘り下げていくのは後からでも良いかもしれません。
ここからは交流会のあるテーマに直接関係する話ですが、情報共有、情報交換の場があるとLSLに関わる人達全体にメリットがあるということを再認識させられました。一部の有志への負担が大きくなるという問題を回避しつつ、何らかの場を設けることができると良いですね、という話には賛成です。
各セッションで共通した話として、LSLの仕様への不満、LSLに関する公式・非公式(カードの情報を登録していないとSLForumを見れないという問題もあります)の情報不足というものがありました。仕様に関する不満は、日本語圏のコミュニティーで話し合ったことをまとめてJiraに登録するということも考えて良いと思うので、なお更何かしらの情報共有の場(日本語で)があるというのは良いことだと思います。
今回のイベントもそうですし、今後情報交換できる場所があれば良いなぁという話にも言えることですが、場所=SIMの確保は大変です。今回は知り合いに頼んで貸してもらったという形のようですが、スポンサーを募るのもいいなぁと思います。よく「企業SIMに人が居ない」と言われますが、公開直後はほとんど人が来ないようなSIMは一部でも開放してもらえるとその方が企業イメージが良いのでは、と勝手なことも思ってしまいました。
交流会では「やっぱり皆そう思ってたのか」という話題が多かったのですが、逆に「去年と違って人も多く、集まる場所も分散したため、交流が減った」という話も聞きました。確かに今年の初め頃は有名スポットも限定されており、ブログで情報発信している人も非常に少なく、またjpwikiもあったので、日本人ユーザーの情報共有の場というのが存在したんだと思います。土地を所有、もしくは借りやすくなったおかげで自分の土地で作業する人も多くなり、結果として交流が減ったということも確かにあるのかもしれません。面白いことをやっている人が居るのにそれを知らない、ということが増えたとも言えます。興味深い点でした。
また長くなりそうなので、とりあえず今日はここまでにしておきます。最後になりましたが、イベントに関わっている方々には感謝しています。
2007年10月19日
セカンドライフツアーに参加しました
以前にも感心しましたということで紹介させて頂いた渡辺千賀さんのブログでセカンドライフツアーのお知らせを見て、珍しくイベントに参加してみました。(セカンドライフセミナー をやるというのはもう少し前に告知されていましたが、in worldでツアーをやるというのはこのエントリーを見るまでわかりませんでした。)
人数制限があるかもしれないということで少し早めにログインしましたが、 Mapを見ると既に集まり始めているのであわてて現地に飛びました。RLの方でハードウェアのトラブルがあったようでなかなか開始できないなど、スタートからかなり混乱していました。
さて、カメラの音がバシャバシャしていたせいもあって、自分ではSS撮りませんでした。知り合いの方だけでも既に数人がブログにエントリーをアップされているので、詳しい様子やSSはそちらをどうぞ(^_^;)。
Second Life の Chika さんツアーにインワールド参加(innxブログ)
Net Nite (ネット・ナイト)@stereo(Ramona Forcella's Day Off)
私の感想は、以下のようなものです。
訪れる場所の作り手・オーナーさんへのインタビュー付きというのは非常に面白い。
普段一人でうろつくだけでは気づかないところに気づく可能性もあります。
Chikaさんがズバズハ質問してくれて非常に興味深い話が聞けた。
例えば「どれくらい売り上げがあるのか」は仮にオーナーさんと話す機会があっても相当親しくなければ聞けません。
RL・SL双方同時に説明しながら操作もこなすのはかなり大変そう。
途中までマイクを手に持っていたそうです。スタンドマイクやピンマイクを使えば良いのですが、念入りに準備する余裕のあるイベントでなければこの辺りもその場になってみないとわからないということですね。
ラグで困るということはなかった。
Bare@Roseに行くのかな?と思った人が他にも居たようですが、よく考えたら皆でわらわら行ったとしても遭難するか落ちるかです。面白いSIMであっても混んでいる場所はツアーには向きませんね。
SLでもツアーの引率は面倒。
特定のアバターを追従するオブジェクトでも使えば良いのではと思いましたが、Kowloonのように細い道が続く場所を見ながら移動するのにはあまり役に立ちません。またテレポートにも対応しなければいけないので、このあたりをサポートするツールがあると売れそうです(いくつかあるかもしれませんが)。
結局踊っている状態のChikaさんを追いかけるのが一番わかりやすかったので、単に引率者が目立つだけでも効果はありそうです。
VoiceでRL会場の音を聞けるのは一体感があって面白い。
RL向けの説明には自分も既に知っていることが多く含まれていましたが、「こんな説明をしているのか」とわかるのはなぜか面白かったです。
肝心のChikaさんだけVoiceが聞こえていなかったようでVoiceでのインタビューができず、そこだけは残念でした。
Voiceだと引率者に引き離されたり先にテレポートされるとなんだかわからない。
特にKowloonでは縦に長くぞろぞろと歩く必要があり、あまり引き離されると声も聞こえなかった人が居るのではないかと思います。これは引率者がいくら気をつけても仕方ない話なので、Stickam等を利用すると良かったかもしれません(そういう仕組みの紹介はされていましたが)。
必死に追いかけてることを訴えるとChikaさんが「すまぬ」と発言されたりして実は結構面白くもありましたが、あまり操作に慣れていない人、PCの描画が遅い人にはつらかったかもしれません。
in worldのツアーガイドというのもあると聞いた気がしますが、今回のようなイベントのサポートビジネスはあるんですかね?あまり優秀なガイドが増えてin worldが団体さんで溢れても困るかもしれませんが。
参加者側としても少々疲れた部分がありましたが、全体的に内容が面白かったので参加できて非常に良かったです。運営側の方々は大変だったと思います。関係者の方々、本当にありがとうございましたm(__)m
2007年10月17日
ユーザーが感じる不満とメディアによるSL批判のズレ
書きかけのままタイミングを逸してしまった内容ですが、書き足していくとどんどん長くなるので一旦公開してみます。
以前LSL関係の情報収集とかLindenLabは説明下手?というエントリーを書きましたが、CnetJapanのオンラインパネルディスカッションで調度「mixiもGREEも、コミュニティ運営は難しい?」というのが始まっていたので、また似たような話です。
最近行われたMixiのデザイン変更が話題になっています。Mixiを良く利用する方ならご存知だと思います(ソラマメでも管理画面について似たようなことがありましたね)。また一部のプラットフォームで表示が崩れるという問題もあったようです。
ちょっと話がそれますが、個人的にはMixiのデザインもスッキリして構造的(XHTML+CSS)にもやっとまともになったという印象でした。ところがいわゆるWeb系の仕事に関わっている人達からも非難があがっているようで、Allaboutにはちょっと理解できないようなコメントも紹介されています。あえてどのコメントが、とは言いませんが結構びっくりできます。ここで専門家としてコメントしている方々は仕事に影響ないんでしょうか。※1 と思ったらやっぱりこういうこと書いてる人も居て一安心(?)。
話を戻して、何がSecondLifeと関係するかというとやはり「サービス提供側が行った変更に、ユーザーが反発する」という話です。今回のMixiの場合は技術的な観点で設計変更し、ついでにデザインもすっきりさせたんだと思いますが、思ったよりも反発が大きかったようです。SecondLifeでもバグの修正をしただけのつもりだったのに「勝手に動作を変えられた」という騒ぎが一部で起きています。
Mixiの場合は正直なところ「慣れの問題」が大きいと思います。また文句のない人は黙っているはずなので、単に文句だけが目立ってしまったという側面があるようです(Cnetのディスカッションでそういうコメントを見ましたが、よく考えればこのような問題には共通することですね)。
一方SecondLifeの方はデザインが気に入らないといった好みの問題だけではなく、公式なLSLのドキュメントをろくに用意しないのに「本来仕様としてはこれが正しいでしょ」とか平気で言ってしまうスタッフが居ることも大きな問題だと思っています。その担当者個人としては当たり前のことなのかもしれませんが、Viewerをインストールしたときに付いてくるドキュメントからそこまで推測しろというのはちょっと厳しいと思います。
結局問題の原因は「説明不足・コミュニケーション不足」です。「今はこういう動作をしていますが、バグなので注意してください」という周知がされていれば、もしくは「将来のリリースで動作が変わるのでベータGridでテストしてください」といった対応をしていれば、あわてて元に戻してRollingRestartという事態にはならなかったはずです。
もっと一般のユーザーにも関係しそうな話ではHugePrim(MegaPrimの方が一般的?)の問題について古くからのユーザーの間でも不満が出ているようです。HugePrimを認めないことによるメリットが理解されればユーザー側も使わないでしょうし、HugePrimを認めても実はあまり問題がない、というのであれば認めて欲しいユーザーが多いと思います。こういった問題はまたJiraを見ましょうという話なのかもしれませんが、Lindenさん公認の遅さを誇るだけに何かを調べるのちょっと大変です。(Wikiの方にもまとまった情報は見あたりませんが、探し方が悪いんでしょうか)
と、大体以上のようなことを書きかけでしたが、公式ブログにMegaPrimについてのエントリーが出たので放置してました。熱心に活動しているユーザーの声はやはり届きやすいのか、夏以降高まっていた不満にLindenさんが答えたのかなぁと思って期待しています。
この手の愚痴は全て「ドキュメント不足」が問題と言いたいところですが、(日本語版の場合は内容が古いかもしれないという)Helpすら今更ながら読んでみると結構知らなかったことばかりなので自分自身は「文句言う前にHelp読め」と言われそうです。ただし情報を探しずらいのは確かです。いろいろと模索中のサービスなのでそこまで手が回らないのかもしれませんが、どうも「どうせ皆Geekなんだから言わなくてもわかるでしょ」という発想も(Linden側に)あるような気がしています。
セカンドライフがブームと聞いて普通の人がわんさかログインしている状況ですが、サービス提供側はそれに対応しきれなかったというか、気にしていなかったということはないでしょうか。今ではサポートにPCの使い方の質問まで来るようですし。
メディアによるSL批判がしっくり来ない理由の一つにこのあたりの問題もあるのかもしれません。SLユーザーが感じる不満(ドキュメント不足、サービスが不安定)と、メディアが良く話題にするユーザーの少なさ(もしくは知っている人の数と実際に使ったことのある人の数など)は全然次元の違う話です。大手のメディアによる記事だけ読んでいると「SecondLifeではin worldで金稼ぎができる。システムもある程度安定していて日本語での利用も問題ない。」と錯覚してもおかしくない気がします。
どうせSL批判をするのなら、「要求されるPCスペックが高いことなんて他の不具合に比べたら大したことない」とか、「日本語版って言ったって未だに日本語が収まりきらないUIがある」とか、そういう話をすればいいのに、と思うことがあります。
Mixiの場合と違って「一部のユーザーの不満が目立ってしまう」のではなく、「本当に不備の多いサービスだけど、それでも魅力を感じた人が使っているサービス」というのがSecondLifeではないでしょうか。「今日もFriends見えないねぇ」とか「今日はよく固まるなぁ」とか言いながらも毎日ログインしてしまう人が増えている、というのが現状です(よね?)。MixiやGREEの問題と似た部分があるかなぁとも思いましたが、この点では全然レベルが違うかもしれません。
話を強引にまとめると(?)、LindenLabにはGeekじゃない普通の人のことも考慮したドキュメントの充実を期待したいですし、日本の大手メディアには「実際のユーザーによる定期的なレポート」も期待したいです。ということが言いたかったんだと思います。
2007年10月10日
値上げ?(噂話)
SLWatchさん経由で「土地代の値上げがあるかも」という噂が出始めていることを知りました。元ネタはSecondLifeInsiderです(元ネタといっても本当に噂話のような記事でSLWatchさんでも「根拠が薄い気がする」という注意書きがついていますし、SecondLifeInsiderの方にも詳細は不明と書いてあります)。
※(補足)LindenLab側も噂が一人歩きする危険を感じたようで、公式ブログにこの件に関するエントリーがアップされました。少なくとも今年中の値上げはないし、具体的な値上げの予定もないそうです。更に料金体系についていろいろ検討中ですよ、ということも書いてあります。
タイトルには「Tierが$195から$295に値上げされそう」とありますが、よくよくリンク先も読んでみると昨年LindenLabが公式ブログにも書いた以下の内容(意訳)が根拠になっているようです。
2006年冬以前からのLandOwnerに対するland feeが$195のままだったのを2007年までは値上げしません、値上げする場合には60日前までに通知します。
2007年が終わる60日前までに通知ということで、10月末までに発表されて11月から適用とう推測になっているようです。要は据え置きだったPrivateIslandのLand Fee(広さに応じて課金されるLandUseFeeとは違います)のことしか言っていません。以前からのLand Ownerには確かに大きな値上げ(1SIMあたり年間で$1200)ですが、その後急激に増加したPrivateIslandのOwnerは既にこの値段を支払っています。
もっとも、現在の1SIM分のLand Use Feeが$195なのでそれも同レベルまで値上がりすることまで心配しているのかもしれません。もしそうなったら確かに全体的にインパクトの大きな話ですが、あくまでも推測でしかないので今は心配しても仕方ありません。
この元ネタのリンク先の一つを読んでみると「支払いをしていないユーザーはMentorから外され始めている」というそれこそ未確認の話になっています。たまたまその文句を言っている人が古くからのIsland Ownerなので今回の値上げがあったらEUのユーザーはさらに大変だという話もしていることから参照されたようです。確かに古くからのOwnerでEUの住民にとって、この値上げが実施されたら大変なことです。
ところで古くからのOwner=持っているSIMはサーバが古いということだと思いますが、それでも本当に値上げするんでしょうかね?サーバの性能の違いをイマイチ実感として理解できていませんが、もし違いがあるとすれば値上げは相当反発をくらいそうです。
今回の話は噂の段階なので置いておくとして、プレミアムアカウントの料金や土地代というのは難しい問題だと思います。長期的にはGridの仕組みを拡張して独自GridやSIMの接続料を徴収するという可能性もあるようですが、あくまでも先の話です。今のところ収入源はSIMや土地の販売とプレミアムアカウントの料金、土地代だけだと思います。
一部の熱心なユーザーが料金を支払うことで成り立っていたり、サポートも手が回っていなくてボランティアに頼らないと向上が見込めない状況では、値上げという問題にはユーザーも敏感になるのが当たり前のような気がします。こうなると、実際まだ使用していないけどとりあえずSIMを押さえている企業というのはある意味スポンサーとしてありがたい存在のように思えてきます。活動していなければサポートにも負担がかからないわけですし。
また何だかわからない話になりましたが、噂話をきっかけに値上げが少し心配になったというお話でした(?)。
2007年10月08日
チャットのUIを改善できないでしょうか
私は人ごみ(チャットが飛び交う場所という意味)が苦手です。基本的には「誰が何を言っているのかわからなくなる」からです。皆が一つのことについて話し合っている場では多少わき道に逸れる人がいても大体なんとかなります。ですが、単に人がたくさん居るだけの場所だと同時にいくつもの会話が入り乱れることになり、話を追うのに疲れる、ということです。
ものすごく下らないことかもしれませんが、自分には結構重要な問題です。オプジェクトがオープンチャットで色々と説明してくれるのさえ邪魔だと思うことがあります。Muteという機能があるので使えば良いのかもしれませんが、解除が面倒なので使ったこともありません。
ちなみに私は普段チャットが吹き出しで表示されるようにしていますが、皆でわいわいやる場合はこれも厳しい場合があります(読み終わる前に消えたりするので)。かといって吹き出しなしでズラーっとスクロールされるだけなのもちょっとつらいです。
「じゃあどうすればいいんだろう」と考えるとイマイチ良いアイディアがありませんが、こんなのはどうでしょうか。
- 輪に入っている人だけにしか見えないチャットというモードを用意する(現在のオープンチャットとは別に)。
- 誰が同じチャットの輪に入っているか、視覚的にわかるようにする(Voiceのように頭上に何か浮くとか)。
- 簡単に輪に入れるし、抜けるのも自由。
グループIMとは違い「明示的に参加の意思を表明しないと見ることができないチャット」ということです。参加しない限りは「あの辺の人達がチャットしてるんだな」というのが視覚的にわかる、というものです。もう一つグループIMとは違い、誰でも参加できるというのも重要です。
「自分が積極的に参加するつもりのないチャットはテキストが小さい」というのも良いかもしれません。
既にいろいろと考えている人が必ず居るはずなのでまずJiraを見るべきですが、調べてみようと思いつつ一度も調べていません。たびたび思い出しますが、毎回「そういえばそんなことも考えた」と思い出しておしまいなので、完全に忘れてしまわないようにメモということで。。。。
2007年10月06日
期待したサービスは消えてしまう可能性が.....
以前アップしたエントリーでコメントを頂き「そういえばそうだ」と気づいたこともあって、ここしばらく「企業が宣伝以外の目的でSecondLifeを利用している実際の例」 が気になっています
探し方が悪いこともあって良い例があまり見つかりませんが、「会議室の時間貸し」のようなものはサービス提供者が見つかります(日本でも英語圏でも)。ただしこれは利用者がどれほど居るのかがわからないので、この分野の需要があるのかわかりません。
この他にも「3Dの世界で遠隔地の人同士がコミュニケーションを簡単に取れる」という特性を生かした例として「語学教室」や「モデルルーム(しつこいようですが)」があると思います。後者はサービス提供者がちらほら出てきているものの、こちらも利用者数や効果は全く不明です。語学系は比較的有効に活用されているようですが、ビジネスとして成り立っているかと言うと、やはり不明です。ボランティアベースのものは活用されているようですが。
ここでふと思ったのが、自分が「これはいけるんではないか」と思った分野では特に目立った成果(ビジネス的に)がないなぁ、ということです。このことは今までに自分が「良い」と思ったけど消えていった製品やサービスのことを思い起こさせます。私が過去に「こうなればいいなぁ」とか「こうなるだろう」と期待もしくは予測したものは、かなりの確率でダメになっているか、普及が遅れています。
例えば「TVとPCの融合」です。今あるような「PCにTVチューナーを仕込みました」というような下らないもののことではなく、「ネットでデータを流し、最初からデジタルデータ」という意味です。これが2005年までにはかなり普及しているだろうと思っていました。なぜかというと、チューナーを仕込んで見かけ上PCとTVが一体になった形の物は、録画機能は別として少なくとも12年前には実用的なものが簡単に手に入りましたし、自分でも使っていたからです。この便利さを見れば、もう一段階先を望む人が増えると思いましたし、デジタルブロードキャストを見越して早々に融合させるべきだという論調の記事を読んだ記憶があります。また、その時点で既に日本は光回線を他国に先駆けて全国に敷設する目処が立っていました(少なくともNTTはそう公言していたはずです)。
ところが見事に予想は外れました。ADSLの時代が長かったですし、「地デジ」が示すように昔ながらの電波で飛ばすTVが今でも主流です。
またOSの普及についても大きく予想が外れています。例えばその当時それこそTVパソコンとして使っていたマシンのOSはOS/2(当時既にWarp)で、その上でWindowsを動かし、Windows専用のTV視聴ソフトを使っていました。今のSecondLifeも真っ青な勢いでクラッシュしまくっていた当時のWindowsでしたが、OS/2自体は安定していて落ちないのでPCの再起動(当時は猛烈に時間がかかりました)が不要というとても快適なものでした。そこで「Windows向けアプリが主流だとしても、これだけ安定性が違えばOS/2も一定のシェアを取るだろう」と思ったものです。結果はWarpも全く売れず、早々に開発を終了した挙句につい最近サポートまで完全に終了してしまったはずです。
もっとメジャーなケースでは、NetscapeがこうもあっさりIEに負けてしまうというのも全く予期していませんでした。
逆のケースもあります。Yahooがリンク集を公開し始めた頃、私はこれがビジネスにつながるとは全く気づいていませんでした。また後のGoogleにしても、他のサーチエンジンが出てきて負ける可能性があると思っていました。HDDも不揮発性のメモリに取って代わられると思っていましたが、まだまだです。
というように、ちょっと例を挙げるだけでボロボロ出てくるほど私の予想はことごとく外れます。とすると、今私が気に入っているSecondLifeも非常に危ないのでは?と、ちょっと不安になります。
まだこういったプラットフォームが一般に普及するには時間がかかりそうですし、LindenLabが検討しているGridの拡張なども時間のかかる話です。その間に別のソリューションが出て来る可能性も大いにあります。
便利であればLindenLabが提供するサービスでなくて全く構いません。ですが、SecondLifeには良い部分もたくさんあると思っているので消滅はして欲しくありません。分析も何もない下らない話で、読んでしまった人には申し訳ありませんが、とにかく良い方向に発展していって欲しいと思います。
2007年10月05日
LindenLabは説明下手?
VATに関するFAQが公開されました(英語でPDFです)。今のところ自分には直接関係ないものの、非常に気になっていた点についていくつか答えが出ているので、ごく一部だけ「私はこういう風に理解しました」という形で紹介します(このあたりも日本語訳はLLではなく第三者によって用意されるんでしょうか)。
疑問:「今までVAT収めてなかったの?」
答え:「収めてました。でももう負担するのは限界です。 」
今まではLLが負担していたけどもう勘弁してください、ということですね。特にドイツやフランスなんでしょうか、EUのユーザーが増えることがこういう形で影響するというのは想定するのが難しかったということでしょう。
疑問:「EUのお客さんからの支払いにL$もPaypal経由もあるけど、どう対処すればいいですか?」
答え:「税法専門の弁護士に相談してください」
世界と簡単につながりはするものの現実世界でのルールは無視できないし、LindenLabは単にサービスを提供しているアメリカの一企業に過ぎないので当然と言えば当然かもしれません。このあたりは明確な運営者が居なかったインターネットと違って「LindenLabが運営する世界の中での経済活動」ということで、なんだかややこしいですね。
疑問:「でもLindenLabはEUにもオフィスなかったっけ?」
答え:「あくまでもユーザーはアメリカのLindenLabのお客さんです。」
なので、今回のような対応(EU外のサービス提供者がEU住民にサービスを提供)になりますということなんですね。将来的にもこの方向でいくんでしょうか。もしSecondLifeが今以上に発展してしまったら、このやり方は難しいんではないかと思いますが.....
疑問:「アメリカの消費税をEUの住民に負担させていないの?」
答え:「二重取りはありません」
「LindenLabが提示している料金にはVATが含まれて居ません」とも言っています。要は完全に外税ですよ、ということですよね(で、今まではVATをLindenLabが負担していたと......)。
更にTownHallMeetingを開くそうなので、今までなんだかよくわからずに不安だった人達にも理解する機会が提供されたと言って良いと思います。余計な話ですが、TwonHallMeetingは効率を考えてVoiceで回答するそうです。チャットだと確かに効率は悪いんですが、ログが簡単に残せるので英語が得意でない私なんかはMeetingはチャットの方がありがたいです。もちろん私は関係ないのでそもそも行かないんですが。
公式ブログにエントリーが上がっているので、そのうち日本語訳も出てくるんだと思います(日本語訳されている方々には本当に感謝しています)。(またまた余計な話ですが、このエントリーのタイトルはSLWatchさんテイストです。SLWatchファンなんでしょうか。)
さて、最初からこれらを提示していればもう少し騒ぎも小さかったような気がしますが残念ながらそうではありませんでした。おかげでサポートには相当負担がかかったと思います。このエントリーで言いたかったことは、要はこの点(=説明不足)です。LindenLabとしての公式な発表があっさりし過ぎたり遅れたりするので不必要に文句が殺到し、余計にサポートが大変になっていないかなぁ、ということです。
OfficeHourもそうですし、開発に一部の住民を巻き込んでいることもそうですし、LindenLabは結構オープンに面白いやり方でSecondLifeを発展させていると思います。ですが、説明が下手で反感を招いていることが少なくないような気がしています(某Nockさんの受け売りですが)。
調度GREEでも経営者の不用意な書き込みが騒ぎを大きくしたというCNETの記事を読んだばかりだったので(GREEのはもうちょっとお粗末な感じもします)、「良かれと思ってやっているのにユーザーから不満が殺到する」というのは(サービス提供側にとっても、利用者にとっても)非常にもったいないなぁと思いました。マル。というお話でした。
2007年10月05日
SLViewerが動作しないPCが多いという問題
この前のエントリーで触れたLSL関係の問題はさすがに早速対応してくれたようで、本日修正が入りました。これで多くの家具屋さんもホッと一息なんでしょうか。
さて話はガラッと変わりますが、Second Lifeについて「企業SIMは実は閑散としている」とか、「操作が難しい」とか「敷居ハードルが高い」とか「日本語版のくせに日本語の情報が少ない」とかいろいろ言う人が居ますが....まぁその通りなんですが、現時点での有効活用を考えた場合に一番困るのは「自分のPCではViewerがまともに(もしくは全く)動かない」というケースだと思っています(2007年10月現在)。個人的にはその他の問題は正直あまり気にしていません(物販をしようとか考えてませんし)。
古いPC、企業向けのグラフィック関係が弱いPCはかなり厳しいと思います。SL参入のためにグラフィックカードを刺したPCを用意した、という企業の方も少なくないのではないでしょうか。そもそもログインできないとなると、いくら「in worldで面白い体験ができます」と言ったところで「なるほどぉ、すごそうですね.....」でおしまいです。
これももちろん将来的に改善されると期待していますが、いつまで待てば良いのかわからない以上何か対策が必要です。
例えば
私:「ムービングエスのSL支店では軽トラックに積める荷物が感覚的にわかるような展示をしています」
お客さん:「へー、でも自分のPCではViewer動かない」
で終わるのではなく、「だったらその(in worldの)様子を動画に撮ってあるのでお見せできます」というだけでもSecondLifeの活用範囲が広がるのではないでしょうか。
最近動画投稿サイトも多いしマシニマも珍しくなくなってきているので、ふとそんなことを思いました。というエントリーでした。まだコンテンツ用意していませんが。
(ところで「SecondLifeに参入」というのはどういう状態のことを言うんでしょうかね......)
2007年10月02日
LSL関係の情報収集
今回のRollingRestartでサーバ側に予期していなかった変更が加わっているということで、一部で大騒ぎになっています。既にJiraにもポストされていて、Voteがわんさか付いている状態(英語)です。
これは「Objectに座っているアバターをプリムと同様llSetLinkPrimitiveParameters()で操作できた」のが「できなくなった」という問題だそうです。家具に仕込んだりして便利に使われているテクニックだそうで、これは影響がでかいというブログのエントリーがちらほら上がり、それで初めて知りました。
Rolling restart fixes bug, angers many scripters(英語)
私はそもそもこの使い方を知らなかったので全く影響がないので一安心です。では何でわざわざこんな話題を取り上げるかというと、日本語のブログではあまり話題になっていないようなので、なんでだろう?ということです(英語圏の人騒ぎすぎ、という程軽い問題でもないように思えるので)。
私はLSLについてまだ初歩的なところを少しずつ勉強中という段階なので、英語のForumやその他の詳しい人が見そうなところはほとんどチェックすることがありません。今回はたまたま見た(LSLとは特に関係のない)ブログで騒いでいたから気づいたというだけです。日本語でこういう問題を扱うのはSNSという場合が多いんでしょうかね?
このテクニックは定番らしいので使っている人も多いのかなぁということで、ざっとソラマメのエントリーを見渡しましたが、あまり目につかなかったので、ふと気になりました。こういった情報を知るのに日本語でどこか良いサイトありますかね.....
(皆さん夜にログインされると思うので、時間的にこれから問題になるのかもしれませんが。)
ちなみにJiraを見ると「この問題については以前担当のLindenさんと話したことがあるけど、一般に周知をせずに今回の修正に入れ込んでしまった」という書き込みをしている詳しい人が居ます。ですが未だに公式ブログには何も出てこないしJiraにもLindenさんからのコメントがありません(※)。何か事実関係の把握に手間取っているんですかね。最近LL対応が早くなってきたような気がしていただけに、この間はちょっと気になります。もしかして騒いでる人の勘違いだったとかいうオチは.....さすがになさそうですね。
※現時点(日本時間の08:00)では複数のLindenさんからコメントがついており、動作を元に戻す修正に入っているそうです。所詮Hackなんだからどうのこうのとしつこく書いてるLindenさんのコメントはどうかと思いますが、まぁ対応してくれているようでなによりです。
2007年10月01日
消費税?(その2)
数日前にもエントリーを書いたEU住民に対するVATの件ですが、コメントで指摘を頂いて興味が沸いたので調べてみたところ、あくまでも「EUでは明確に規定されている税制」に基づいた課税であるため、その他の国で同様のことが起きる可能性は何とも言えないようです。例えば日本では同様のケースに対する課税は(少なくとも現時点では)されないようです。このルールは4年ほど前から適用されているようなので、EUへの納税自体は当然LLとしても考慮しているべき問題だったと言えます。
参考にしたのはJetroのサイトにある情報です。(http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search-text.do?url=0100EU000304)
B2Cの場合には第三国からサービスを受ける個人ではなくサービスを提供する第三国の事業者が課税される。
日本のケースについてはSL総合研究所さんのエントリーを参考にしました(ここから更に参考資料へのリンクがあります)。
で、気になっていたのは「じゃあ今までLLは税金払ってなかったんですか?」という点です。これに関して公式なアナウンスがないなぁと思っていたら、こちらのブログエントリーにRobinLindenさん曰く、というお話が出ていました(ソースが良くわかりませんでしたが)。それによるとLLがEUにVATを収め始めたのは7月だということです。
(ちょっと逸れますが、このエントリー自体は「EUの住民だけE-CommerceにかかるVATで損をするような状況について、EUの人達は文句を言わないの?」という問いかけです。)
今回いきなり消費税負担をユーザーに通知したのは、「公表してしまったらすぐに実施(税金徴収のことだと理解しました)しなければいけないので、事前にお知らせだけして猶予期間を設けるという手段は取れなかった」と言っていたLindenさんが居ました(私が英語を理解できずに勘違いしたのかもしれませんが)。なので「公表=その時点から消費税を納める」というシナリオなのかと思っていました。でもこの7月という話が本当だとすると、本当に「なんでこのタイミングでユーザーに負担させることにしたの?」という疑問・不満が噴出する気がします。
このEUのルールには最低の税率も目標として定められているようで、それ(最低)が15%なんだそうです。免除の制度もあるようですが、その条件までは知らないので大半のユーザーが免除の対象になるのかどうか、よくわかりません。仮に大抵の人はやっぱり課税されちゃいますということになると、「LL側の努力でいくらか吸収してくれないのか?」という批判は出てきそうですね。
簡単に世界中の人とコミュニケーションがとれるのがSLの大きな魅力ですが、Lindenドルと自国通貨の価値の違いや、今回のような税制の問題が出てくると運営も難しいと思います。似たようなケースが考えられるものとして例えばSkypelがありますが、あれはどうなっているかというと.....
こちらのページ(Skypeの日本語のページ)には
Skype は先日、当社の本拠地であるルクセンブルグの税当局に対し、EU 加盟国の低税率地域の取り扱いを明確にするよう求めました。当局から回答が得られるまでは、15% の VAT を課税する必要があります。Skype から VAT の受領書を入手しておけば、後で VAT を回収できる可能性があります。
とあります。VATはやはりユーザーが負担しているようです。ただし、本来消費税が15%以下の国の住民も15%(上記の決まりの最低ライン)払う必要があるのか、という点については税当局に確認中ということのようです。まだ制度が浸透していなくて解釈がばらばらなんでしょうか。
LindenLabも専門家と相談して今回の措置をとったという言い回しを繰り返し使っているので、要は結構解釈が難しい問題なのかもしれません。となると、やはり「文句を言う余地もあるんじゃないの?」ということを言い出す人は出てくるだろうなぁ、ということで、この問題は思っていたよりも影響が大きいかもしれない+SecondLifeだけでなく、同様に世界を相手にするサービス(現地法人が直接サービスするのではない)が抱える共通の問題なんだろうなぁ、ということが言えると思います。
但し、現地法人を作ってそこが料金を徴収するような場合はどうしても通貨の差だってありますし、税制も現地の税制に従うはずです。LindenLabが各国に現地法人を作ってサービスするようなことがあれば、今回発生しているような不満も起こりえない、ということですね(?)。
ところでこの問題、3~4年前には今のEUの(電子的なサービスに関する)VATに関する制度がスタートしたようですが、他のオンラインゲームではどうなんでしょうか?「パッケージを買えば接続料は無料」というのなら別ですが、その他の課金が発生するオンラインゲームってないんでしょうか?(ゲームやらないのでわかりませんが、気になります。)
前出のブログエントリーの問いかけにあるように、本来この問題はLindenLabの問題ではなく、EUの制度の問題なんだと思いますが、今のところ説明不足でLindenLabに不満が殺到しそうです。「わかってるはずの問題なんだから最初から明記しとけ」という批判はどうしたって出ますよね。後出しという形になった上に説明不足というのは非常に厳しいと思います。LindenLabも大変だなぁ、というお話でした(自分の方こそ大変だというユーザーも多そうです)。