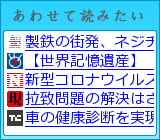2007年10月24日
LindenLabが日本をどう考えているか知りたい
リンデン副社長に聞く、日本におけるSecond Lifeのあり方(ascii.jp)という記事を読んで気になっていたのでメモしておくことにします。
...プラットフォームとして考えた場合は事情が変わってくるでしょう。(プラットフォームを生かすという観点では)日本の企業のほうが、日本人に最適なサービスやエクスペリエンスのあり方を知っているはずですし、どのようなサポートが適しているのかも理解しているはずです。
...私たちが「日本人特有の考え方」や「日本国内のビジネス」の本質的な部分をすべて理解するのは不可能なんです。
「It is your market, you know the best」(日本市場については、日本人がもっともよく知っているでしょ?)ということを言いたいのです。
ということで、サポートについては以前Office Hourとか日本語サポートとかというエントリーでも少し触れた「コミュニティー・ゲートウェイ・プログラム」「グローバル・プロバイダー・プログラム」に期待ということだと思います。
LindenLabのゴールは何かと聞かれて
一言で言えば、柔軟性のあるバーチャルワールドプラットフォームを提供し続けていくことです。
と答えているのに
...「プロダクト」としてのSecond Lifeと「プラットフォーム」としてのSecond Lifeは切り分けて考えなければならない...
とも答えていて、そのプラットフォームとして捉えた部分は前述のように日本人がやればいいじゃん、と書かれており、少し理解しづらい内容になっています(LindenLabはどこまでをサポートすべきと考えかについて)。
言いたかったことは「SecondLifeというプラットフォームを支えるシステムの動作は保障する(ように努力する)」だと思いますが、線引きがイマイチわかりずらくユーザーからの期待とLindenLabが考えるサポートにズレが起きること請け合いのように思います。この辺り、以前Nockさんが書かれていたことは正にそのとおりで、やはり共通の認識が必要だと感じます。
もっとも英語版意外は全てベータ版なので、英語以外でのサポートはそもそも期待し過ぎてはいけないのかもしれません。
今度はサポートとは別の部分です。前述の「日本の企業の方が~」という部分を受けて次のように質問しています。
そのメッセージは誤解を招きそうです。積極的に動く米国人の体質とは異なり、日本人は「何かしらの箱」を与えられるべきと考えることが多いのです。
これに対してこの副社長さんは次のように答えています。
確かに「プラットフォームだけを提供しているのだ」という言い方では「え? 自分たちで全部やれというの? サポートをしてくれないの?」という意味に受け取られるかもしれません。
しかし、これは“関係ないよ”という意味ではまったくないんです。
質問者側はSecondLifeをネットゲームのようなものとして捉えた場合に、LindenLab側がコンテンツ自体用意していないと何して良いかわからないのではないか、と言ってるように思います。どこまでサポートするつもりがあるのかというサポート体制の方に話を進めるのかと思ったのにちょっと意外でした。事実、回答側は「サポート」の面も気にして回答しています。
ゲームとして捉えれば確かに何か用意されていた方が面白いという人が居て当然ですが、それはまさしく日本人の好みにあったコンテンツを誰か(LindenLabである必要はない)が作れば良いのであって、今更この点をついてくるとは思いませんでした。そう聞かれてしまえばLindenLabとしても「日本市場のことは日本人が一番よくわかるでしょ」と答ええるのも当たり前のように思います。
コンテンツの充実や楽しみ方の面で、それほど米国人と日本人の特質の違いを心配する必要があるのでしょうか。元記事を見ればわかるように、インタビュアーはどうもChizzyさんのようです。ご本人は(私よりははるかに)楽しみ方を知っていて日本のin world事情にも詳しい方です。そのChizzyさんがこういったインタビューを展開するということは、日本人が自前でコンテンツを用意して盛り上がるのは難しいのではないかと心配されているのでしょうか。「何をして良いかわからない」という声を心配する必要性を感じていなかったので、この点が非常に気になっていました。
よくよく考えてみるとこのインタビューは「月刊アスキー」に掲載されるそうで、まだまだSecondLifeが「どんなものか」知らない人の方が圧倒的に多いわけです。インタビュアーはそういう人が抱くであろう疑問に触れる必要があります。考えてみれば当然のことながら、このインタビューを読んだ時点ではかなりの違和感を感じたというわけです。まだChizzyさんの意図するところを理解できたか不明ですが(^_^;)
LindenLabが日本という市場についてどう考えているのか全くわからないなぁと思っていたので、このような当事者の声が聞けるのはありがたいと思います。逆にユーザー数多いんだからもっと日本について真剣に考えて欲しい(考えていたら情報発信して欲しい)とも思います。というお話でした。
商標について(その1?)
あけましておめでとうございます
アカウントの登録・情報変更について(その2)
日本的なサービスは期待しない方が良いのでは
アカウントの登録・情報変更について
話しているのはコンテンツのことではなくて例えば「いまのオリエンテーションアイランドは日本人にはワカリヅライ!どうにかしろ!」と文句を言って改善を待つのではなく、「こうしたら日本人に合うと思うからテストや環境面で協力してくれ!」といったかかわりをしていきましょうということではないでしょうか。
Chizzyさんが「何かしらの箱」といったのは、この例で言えば日本人向けのオリエンテーションはじゃぁ LLが作るの?住人が協力して作るの?企業が作るの?といったところを指しているのではないでしょうか。LLとしてはそこまでお膳立てはしないけど、SLのなかに mixi的なエリアや環境を作ってもかまわないし、それを実現するのに技術的なサポートがいるならもちろん協力しますよといったかんじ?たしかに日本的サービス提供からすれば「もうちょっと提供側で作りこんでもいいんじゃない?」と感じるのもわからなくもないデス。が、そこまで LLがやらないところが SLの魅力なんですよね…。
>「ああ、いつも言ってることを言ってるね~」ぐらいにしか感じなかったです。
そう思って読めば特に引っかかることもなかったですね。
言葉の壁が問題でサポートが不十分ということばかり考えていたもので(^_^;)
>そこまで LLがやらないところが SLの魅力なんですよね…。
同感です。
 at 2007年10月25日 18:11
at 2007年10月25日 18:11